お盆を挟んだ長い夏休みが終わって、今日から通常業務モードに戻りました( ;∀;)
猛暑復活…今年は10月になっても真夏日が続きそうという有難くないニュースも聞こえてきますが、次男宅から夏休み期間中に「避暑」名目で預かった「お犬様」と早朝の散歩に出るたび、日一日と頭を垂れてくる稲穂の波を目の当たりにする毎日を過ごしていました。
既に「早場米」産地では稲刈りが始まり、令和7年産新米も出回り始めたようですが、8月下旬から栃木県内でも水田での稲刈りが本格化して来ると思います。
今年は昨年に増してJAや専門商社が提示する「コメの買取価格」の上昇が見込めるようで、コメ農家の期待も高まっているとも思えます。
おいしいお米をたらふく食べたいと思う消費者としてはコメの値上げは痛いのですが、何十年間もコメの生産抑制や低価格路線を強いられてきた生産者の側に立って考えれば、ある程度の値上げは必要だと思いますし、昨年からの「令和の米騒動」も良い機会だったと思います。
その騒動が効いたのか、政府(農林水産省)は「コメの減反政策を転換して増産へ舵を切る」事を表明しました。
読売新聞によると、昨年は、国内コメ需要に比べて生産量は32万トン不足していたという事です。
計算してみると530万俵(1俵=60㎏)という途方もないコメが不足していたことになります。
なるほどコメ不足で値段が騰がる訳ですよね(>_<)
戦後一貫してコメの政策抑制が「農政の一丁目一番地」だった事を考えると「隔世の感」がありますが、今後はインバウンド需要を始め、ジャパンブランドとして輸出にも磨きをかけて行くそうです。
減少する一方の第一次産業従事者の離職を食い止め、自立・自活できる農業従事者数を復活させ、食糧自給率を保持する事は、自国の安全保障上も必要とされる考え方かと思います。
喰える農業へ、現行法や規制の見直しも必要でしょう。
努力して成果を挙げたモノが正当に評価され、そして果実も得ることができる。
そういった農政を期待しています。



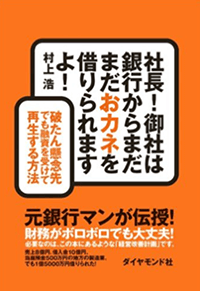
コメント
※コメントは承認制となっております。承認されるまで表示されませんのでご了承ください。